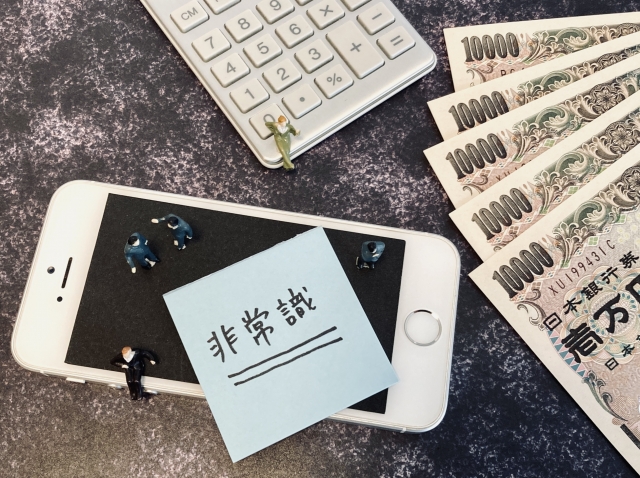廃棄物処理法では、
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう
廃棄物処理法
となっています。
現場では廃棄物かどうかを、どのように判断しているのでしょうか?
廃棄物の定義については裁判で論争になったこともあります。
現在のところ、廃棄物であるかどうかは、「複数の要素を勘案して総合的に判断すること」(総合判断説)となっています。
総合判断説は、行政の通知等で以下のように説明されています。
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること」
しかし、この説明では廃棄物かどうか現場での判断がしずらいですし、いちいちこんなことで判断していたら業務が滞ります。
そこで現場では「取引価値の有無」を便宜的に判断基準としています。
つまりその廃棄物が「売れるかどうか」ということです。
産業廃棄物収集運搬業許可のことなら産業廃棄物収集運搬業大阪代行センターにお気軽にご相談ください。