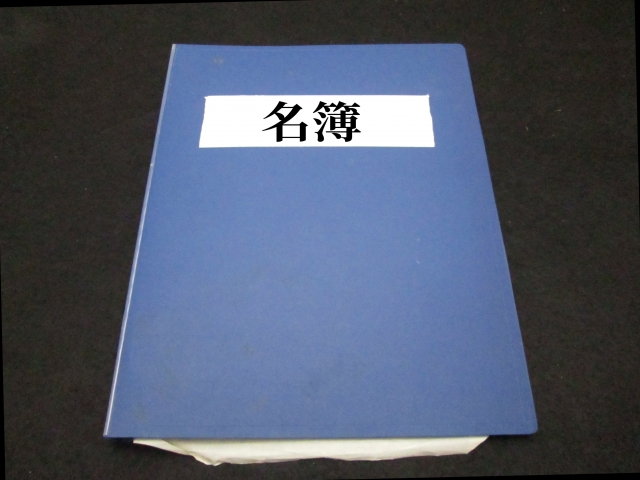運輸支局の職員が無通告でやってきて、法令遵守等をチェックされることを「監査」といいます。(トラック協会の巡回指導ではありません)
「監査」のきっかけはたくさんあります。
一例を上げますと、行政機関(公安員会、労働局、道路管理者、日本年金機構)や従業員、ライバル会社からの通知や通報、死亡事故を起こした場合や飲酒運転をした場合などです。
「監査」が来て違反等が発覚すると、「行政処分等」が行われます。
「行政処分等」とは以下のようなものです。
- 勧告
- 警告
- 自動車その他の輸送施設の使用停止処分
- 事業の全部または一部の停止処分
- 許可の取消し処分
下に行くほど処分が重くなっていきます。
行政処分等が行われる時は、地方運輸局等へ呼び出しを受け、事業の改善について指導され、状況を3カ月以内に報告しなければなりません。
行政処分を受ける営業所を廃止にしても、別の営業所に処分が下されることになります。(処分逃れの対策として)
「行政処分等」の使用停止の処分を受けると、車両が期間を定めて何日か止められます。車両を10日停められることを「10日車」といいます。
また、この場合にはナンバープレートを運輸支局等に預けなければなりません(領置)
違反点数制度
行政処分等が下され車両が止められると「10日車」で違反点数が1点貯まります。「200日車」であれば20点が貯まる事になります。
これが「違反点数」です。違反点数は3年間累積します。
(特例で「Gマーク」事業者は2年になります)
この「違反点数」が一定の値を超えると、車両停止 → 事業停止 → 許可取消し といった具合に行政処分等が重くなっていきます。
この違反点数は同じ運輸局管内で81点まで累積してしまうと許可が取り消されます。取消処分を受けた事業者は「欠格要件」に該当することになり、5年間許可を取得することができなくなります。
違反点数や頻度によっては、増車届ができなかったり、事業規模拡大につながる認可申請を出せなくなったりなどのペナルティも課せらることになります。
以下に国土交通省のトラック運送事業者の違反点数制度の概要を掲載します。
-728x1024.jpg)
運送業許可のことなら運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。