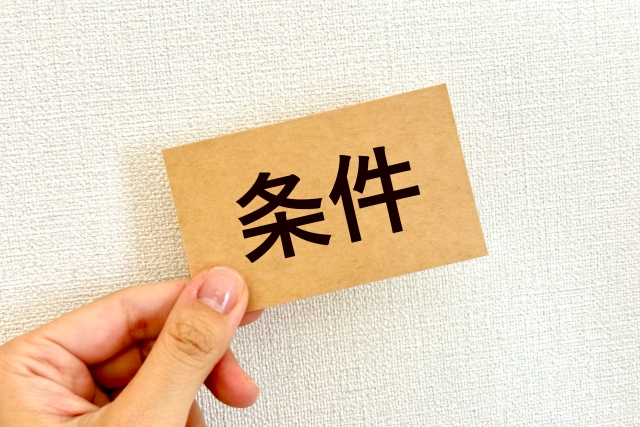道路交通法では、本来の通行目的以外における道路使用について交通の危険、妨害を生じさせる「道路における禁止行為」を規定しています。
また、「道路工事」「工作物の設置」「祭礼」等、公益または社会的習慣上から道路を使用することがやむを得ない行為については、一定の要件を備えている場合にその使用を認めることとしています。
これを「道路使用許可」といいます。
道路使用の許可権者は道路の部分を管轄する「警察署長」です。(同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長となります。)
道路使用許可の対象
道路使用許可の対象となる行為は以下の通りです。
- 道路工事
道路において工事もしくは作業をしようとする行為
道路そのものの工事はもちろん、水道管やガス管を埋設する工事や、主たる工事は道路外で行われていても、工事の一部が道路上に突出し、交通の障害となるものなど、およそ道路上を使用する工事等の全てが対象となります。
例:水道管・ガス管の埋設、更新、保守工事。電気、電話等の設置、保守管理等 - 工作物の設置
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 - 露天・屋台の設置
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為 - 道路においての祭礼行事等
マラソンなど
その他の具体的行為については、各都道府県公安委員会規則に定められています。
道路使用許可の申請者
道路使用許可の申請者となる者は、対象行為をしようとする者(道路において工事等をしようとする者や当該工事請負人)であり、現実に工事等に従事する者(行為者)ではありません。
具体例
Xさんが建築会社Aと新築一戸建ての契約を交わしたとします。
建築会社Aは下請会社Bに工事を請け負わせ、B会社は道路の掘削をC社、水道管工事をD社、ガス管移設工事をE社に分散して下請けをさせた場合、A社は当然申請者となります。また、B社も道路使用の場所、範囲、期間等について全容を把握し管理する者であれば申請者となります。
C、D、E社は仕事を分担しているにすぎないため、申請者にはなりません。
もし、この工事が無許可で行われた場合、違反者となるのはA社とB社になります。
道路使用許可の基準
許可を要する行為について、許可の申請があった場合に、判断をするのは管轄の警察署長になります。
許可(審査)の基準
所轄の警察署長は、申請された路上工事等について審査の上、次のいずれかに該当するときは、許可をすることになります。
- 申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認めるとき
- 申請に係る行為が、条件を付することにより交通の妨害となるおそれがないと認める時
- 申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または社会の習慣上やむを得ないものであると認めるとき
申請された路上工事等の許可の判断は、申請書の記載事項の不備や必要書類の添付等申請に伴う形式的な要件と、申請された路上工事等が、上記の基準に該当しているかなど、具体的な申請の内容を審査して決定されます。
申請にあたって、許可の基準となる事項や疑問点当について、事前に許可を申請する警察署の道路使用許可窓口で相談、確認するようにしましょう。
「道路使用許可」のことなら行政書士伊藤友規事務所にお気軽にご相談ください。