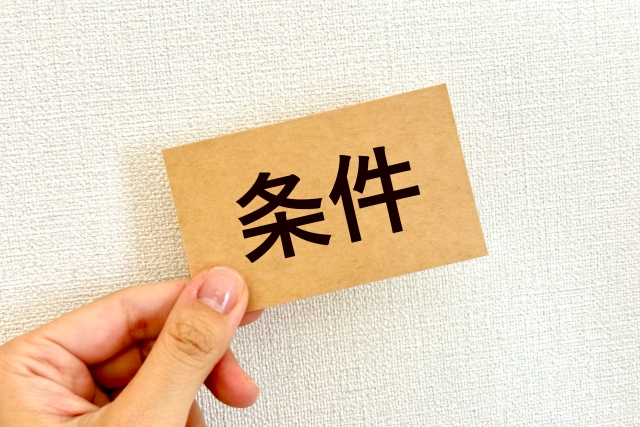
道路上で工事をしたり、祭礼行事をしたりする場合には「道路使用許可」が必要です。
「道路使用許可」を得るためには、行為をしようとする場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。
所轄警察署長は、道路使用の許可をする際に、その許可をしよとする路上工事等が、現実に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除いて、道路における危険を防止し、その交通の安全と円滑を図るために必要な範囲で条件を付すことができます。
許可条件
「許可条件」は、道路を使用するに当たっての遵守事項はもちろん、施行時間や道路使用の範囲等の条件を付することも含まれ、各都道府県の道路、交通状況によって異なりますが、一般的には次のようになっています。
- 施行時間は、原則として昼間は9時から18時まで、夜間は20時から6時までの間とし、通過交通の円滑を確保できる時間帯とします。
なお、工事時間の延長は、許可条件変更手続きや新たな許可申請が必要です。業務等の場合は、所轄警察署に連絡し、指示を受けてください。 - 施行時間外は、埋め戻し、覆工(ふっこう、歩行や交通の支障がないようにする仮設の床)を確実に行い、交通を開放します。
- 作業帯(作業をするエリア)の幅は、車両通行、歩行者通路を確保した上、必要最小限とし、長さは、管路埋設工事はおおむね100m、道路舗装工事はおおむね200m以内が原則です。
- 同一路線においては、他企業の工事等を含めて、作業帯間の離隔は、300m以上を原則とします。ただし、施工場所周辺の道路環境、交通環境等を勘案して、道路交通の安全と円滑を確保するうえで支障がない場合には、現場の実態に応じて300m未満の離隔があっても施工できる場合があります。
- 車両通行路の幅員は、1車線の場合は3.5m以上(大型車通行止めの場合は3.0m以上)、2車線では6.5m以上、歩行者通路の幅員は1.5m以上が原則です。
- 必要箇所に交通誘導員を配置します。
指導事項
許可条件とは別に、必要により注意的、確認的事項について指導事項を付することがあります。
例:一般通行人につきまとったり、立ちふさがったりしない。現場責任者は許可証を携行し、警察官の指示があったら提示することなど。
許可条件の変更および新たな条件の付与
所轄警察署長は、許可を与えた後に、道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じた場合に、先に付した条件を変更したり、新たに条件を付すことがあります。
例えば
- 路上工事等を行うにつき、その許可の期間中に「祭り」等があり、昼間、特に混雑するときは工事を一時中止する。
- 夜間施行を条件に工事等の道路使用許可をした後に、その道路における夜間の交通量が増加してきたことから、さらにその期間を制限する。
などです。
ここでいう「新たな条件」とは、当初の許可には条件を付さなかったが、その後、条件を付する場合と既に条件が付されている場合に、さらに条件を付け加える場合の双方を含みます。
道路使用許可のことなら、弊所ホームページにお気軽にご相談ください。


