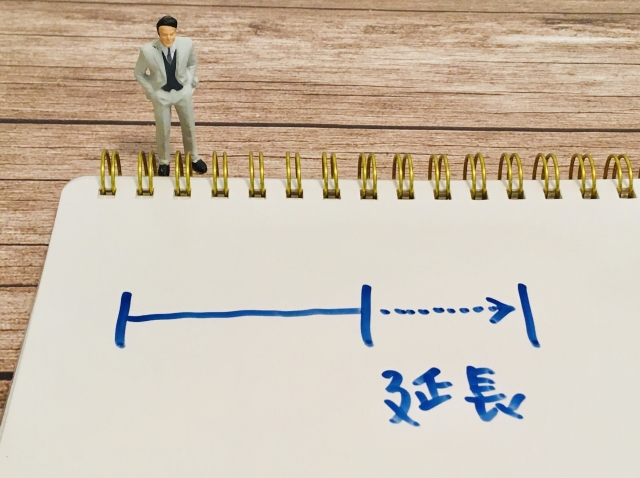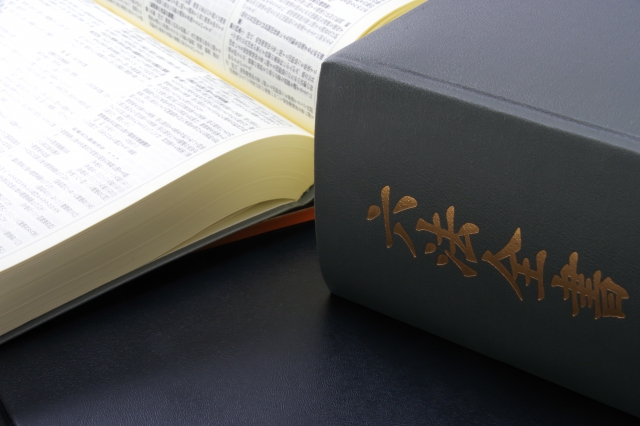農地の権利移転(所有権)や設定(地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借)をする場合には許可が必要です。
上記の許可を受けた者や許可不要の者を除いて、農地等の権利を取得した場合にはその旨を農業委員会に届け出なればなりません。
農地法3条届出が必要なケース
相続、遺産分割、時効取得、包括遺贈(遺言で「財産の全部を遺贈する」や「財産の3分の2を遺贈する」といった遺贈をすることをいいます)の場合には届出が必要です。
相続の時はまずは、法務局で名義変更の登記をしましょう
農地を相続すると名義変更の登記が必要になります。
相続した後も、名義変更の登記をしないで放置していると、権利者(相続人)と登記簿上の名義人が異なることから、将来、真正な農地所有者がわからなくなり、トラブルの原因になります。
また、農地を貸して管理することができなくなります(遊休農地化してしまう)。
遊休農地は、復旧するために一定の経費を要するほか、隣接する農地を所有する農家の作物生産に支障が出る(遊休農地の雑草などが生い茂ることで隣の土地に干渉する)など、迷惑をかけてしまいます。
農地バンク
農地中間管理機構(農地バンク)とは農地の出し手と受け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です。
農地を相続したが、自分で管理できない場合などは、利用価値があるでしょう
届出の期間
農地を相続等により権利取得した場合は、権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、その農地がある市町村の農業委員会への届出が必要です。
届出しなかった場合の罰則
届出しない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を科されることがあります。
農地手続きに関する事なら農地手続大阪サポートセンターにおまかせください。