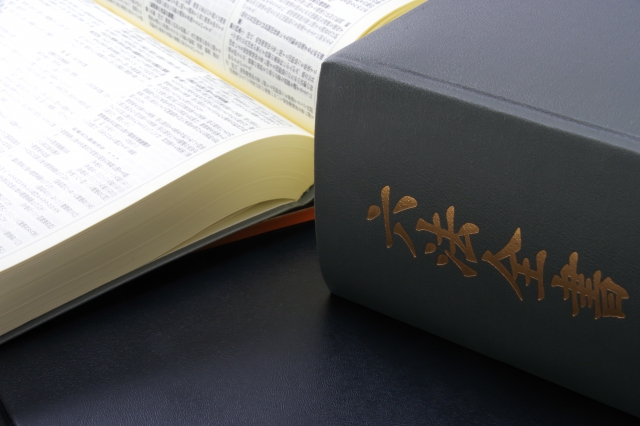
農地は「農地法」という法律により守られています。
それは、農地が農業生産の基盤であり、国民や地域にとって限られた資源であるからです。
第一条
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地法
食糧生産の場である農地は一般の宅地と異なり、農地法により強い公的規制が課されています。
農地の権利移動(売買)、権利設定(貸し借り)、転用(農地を農地以外にすること)を行おうとするときは、契約等に先立って農業委員会等の許可が必要となります。
農地の手続きに関しては、農地法が関わってくることになります。
農地の売買や貸し借りは農地法3条の許可
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法
農地の売買や貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要となります。
3条の許可を受けずに農地の売買等をおこなっても効力が生じません。
農地法3条の許可要件は、農地の権利を取得しようとする者または世帯員等で満たせばよいことになっています。
農地法では世帯員について定義されており「二親等内の親族」と範囲が決められています。(生計を同じにしていたり耕作に関わったいたりなど条件があります)
農地法3条の許可を得るためには、農地を効率的に使ったり、農業に従事していたり、周辺との調和をとれるか?などの要件を満たす必要があります。
農地法による賃貸借は自動的に更新(法定更新)されます(農地法17条)ので注意が必要です。また、いつでも解約できるわけでなく、次に示すような「許可」が必要となります。「農地は貸したら返ってこない」の所以です。
農地法による賃貸借の解約の場合は農地法18条の許可が必要
農地法3条の許可を得た賃貸借の解約には、農地法18条の都道府県知事等の許可を得る必要があります。許可をえるためには、例えば賃借人の借賃の滞納など要件が必要となります。
農地を農地以外にする農地転用には農地法4条、農地法5条の手続きが必要
農地を宅地にしたり、駐車場にしたり当、農地を農地以外にすることを「農地転用」といいますが、農地法では農地を農地以外にすることを規制しており、「農地転用」をする場合には農地法による許可を必要としています。
権利移転(売買)や権利設定(貸し借り)がない農地転用の場合は農地法4条の許可
農地を売買や貸借をせずに農地転用する場合には、農地法4条の許可が必要となります。
農地法4条の許可を得るためには、農地の立地や転用の計画、農地転用の障害となる権利者からの同意、他の農地への影響の防止などの要件をクリアしなければなりません。
第四条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
農地法
権利移転・設定がある農地転用の場合は農地法5条の許可
農地法5条の許可は、農地法4条と農地法3条の権利移動許可を併せ持ったものです。
農地法3条の場合と同様、効力の発生要件であり、農地法4条の場合と同様に転用禁止の解除を行うものです。
許可の申請は当事者(売主と買主等)で行わなければなりません。
農地法5条の許可を得るためには、農地法4条許可と同様に、立地やその他の基準をクリアしなければ許可されません。
第五条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
農地手続に関する事なら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。






