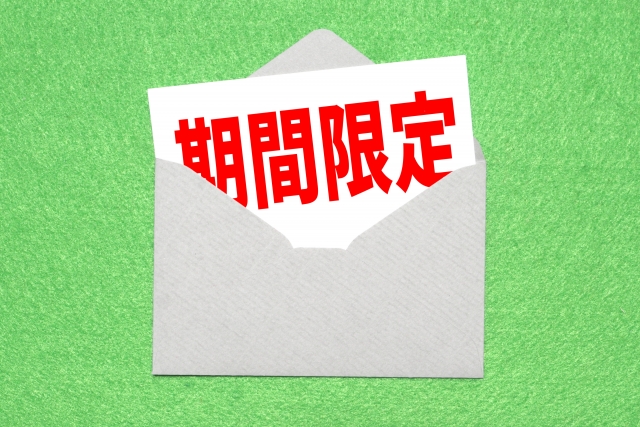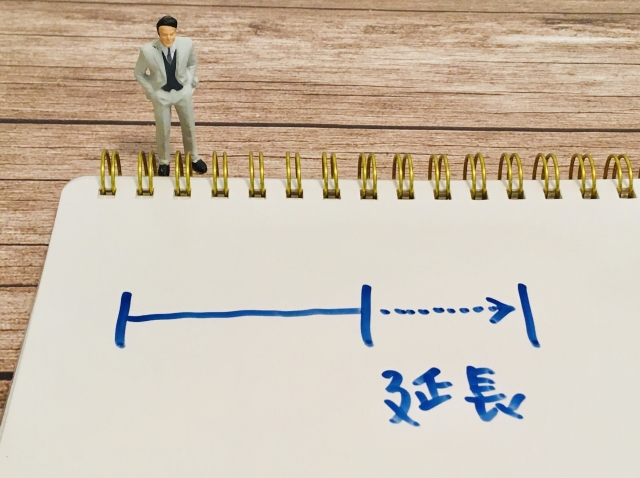農林水産省の「処理基準」によれば、
(1) 農地等の定義
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第4
45号。以下「令」という。)、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「則」とい
う。)及びこの処理基準で「農地」及び「採草放牧地」とは、次に掲げるものをいうもので
あり、これらに該当しない土地を農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)として取
り扱ってはならない。① 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費
を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」に
は、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればい
つでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるもの
と認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。② 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で耕作又は養畜のため採草又は家畜の放牧の目的
に主として供される土地をいう。林木育成の目的に供されている土地が併せて採草放牧地
の目的に供されており、そのいずれが主であるかの判定が困難な場合には、樹冠の疎密度が0.3以下の土地は主として採草放牧の目的に供されていると判断する。③ 「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反覆継続的に行われることをい
い、必ずしも営利の目的であることを要しない。(2) 農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項
(1)の農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記
簿の地目によって判断してはならない。以下省略
農林水産省「処理基準」より
登記記録の地目は農地(田や畑)であるのに、現況は建物が建っていたりなど(宅地)など他の地目である場合があります。
この場合、登記簿上の地目と現況の地目が違っていることになるので、登記簿上の地目を農地→宅地へ変更する場合、地目変更登記(地目変更を含む表示に関する登記は現況主義です。このケースの場合は現況が宅地になる)はすんなりとできるのでしょうか?
この事については、「農林水産省の通知(登記簿上の地目が農地である土地の農地以外 への地目変更登記に係る登記官からの照会の 取扱いについて)」で取扱いが示されています。
登記官は、地目変更登記申請に農地法の転用許可証等又は都道府県知事若しくは農業委員会の農地に該当しない旨の証明書が添付されていないものについては、必ず農業委員会に農地法の転用許可等の有無、現況が農地であるか否か等について照会するとともに、農業委員会の回答をまって登記事案の処理が行われることとなつた。
「農林水産省の通知(登記簿上の地目が農地である土地の農地以外 への地目変更登記に係る登記官からの照会の 取扱いについて)」
この通達では、地目変更登記申請の際には
- 農業委員会の農地に該当しない旨の証明書(非農地証明)
- 転用許可書(過去に届出や許可をもらったのであれば「農地転用届出(許可)受理済証明書等」)
のいずれかの添付を必要としており、無ければ
登記官は農業委員会に対して、農地法4条、5条の転用許可の有無や対等土地の現況について照会するとされています。
照会を受けた農業委員会は現地調査や原状回復命令の対象(違反転用)なのかどうかを確認し、登記官に回答します。
登記官が農業員会からの回答を受けるまでは、登記申請処理が留保されたり、もし原状回復命令事案(違反転用)であれば却下されます。
上記の通達が出た当時の背景として、地目変更(農地→宅地)により土地の売却価格が格段にあがる不動産市場の実態があり、転用許可を得ないで簡易な造成工事のみ実施して地目変更登記したり、市街化調整区域において建築許可不要の「既存宅地(「線引き」前より宅地等であった土地)」の認定(現在は廃止となっています)を受けるための地目変更登記などが散見されたことがあります。
(その結果、法務省と農林水産省が連携してこのような通達が出された)
現在も、違法転用の防止の基準として上記のような運用がされています。
表示に関する登記は現況主義ですが、状況に応じて、必要書類(非農地証明や転用許可書)を用意し、しっかり準備して地目変更登記に臨みましょう。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。
※本記事は農地転用に関する周辺知識の一般的内容を記事にしたものです。上記サポートセンターは行政書士事務所が運営しておりますので「登記」に関するご相談には応じることができませんので予めご了承ください。