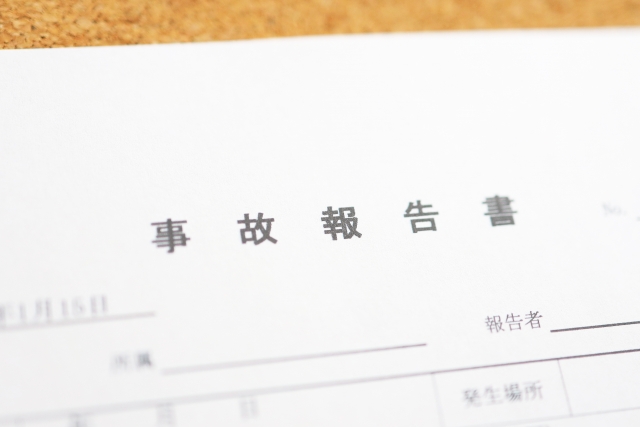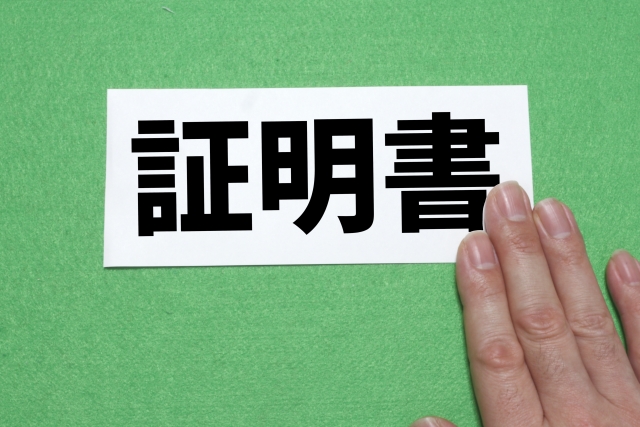他人の荷物を自動車をつかって有償で運ぶ事業を「貨物自動車運送業」といいますが、この事業を営むためには、国土交通大臣の許可を得なければなりません。
申請は、営業所を置く府県の運輸支局に提出します。
では、「貨物自動車運送業」の許可をもらうために必要な費用はどれくらいかかるものなのでしょうか?
他人の需要に応じて、有償で自動車をつかって貨物を運送する事業を「一般貨物自動車運送事業」と言います。
他にも、特定の者を対象とするものを「特定貨物自動車運送事業」、軽自動車を使う「貨物軽自動車運送事業」などがあります。
今回は「一般貨物自動車運送事業」(以下運送業許可という)について説明していきます。
運送業許可取得にかかる費用
運送業許可を取得するためには主に以下のような費用がかかります。
- 事業の開始に要する資金(許可要件)
- 登録免許税
- 専門家に対する費用
事業の開始に要する資金(許可要件)
運送業許可を得るためには、許可要件をクリアする必要がありますが、その一つに「資金計画」があります。
運送会社を経営していく上での準備資金、運転資金を算出し、許可申請から許可日までの間、算出した資金額以上の自己資金を保持していなければなりません。自己資金については「残高証明書」で確認されることになります。
車両数や従業員数、営業所や車庫の賃料、車両についても自己所有なのかリースなのかで変わってきます。各々取得費あまたは1年分や半年分の金額は必要となりますので、900万円で済む場合もあれば2000万円を超える場合もあるでしょう。
許可基準を示す「公示」には以下の用に規定されています。
事業の開始に要する資金(以下、「所要資金」という。)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のア.~カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
ア.車両費取得価格
(分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は1ヵ年分の賃借料等
イ.建物費取得価格
(分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、1ヵ年分の賃借料、敷金等
ウ.土地費取得価格
(分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。) 又は、1ヵ年分の賃借料、敷金等
エ.保険料
① 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分
② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税租税公課の1ヵ年分カ.運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の6ヶ月分
(公示)一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針についてより一部抜粋
所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
登録免許税
申請して許可処分後に登録免許税12万円を支払う必要があります。
専門家に対する費用
運送業を開始し経営していくには当たってはさまざまな専門家がいます。専門家を使う場合は専門家に対する費用が発生します。
許可取得後に依頼する事になる専門家もいるでしょう。
運送業に関係する主な専門家は以下の通りです。
行政書士
運輸局への許認可全般を担当するのが行政書士です。
申請書の作成、添付書類の収集、許可要件の確認・調査、車両の登録、行政との折衝等をおこないます。また許可取得後も各種変更届(役員、車両等)、コンプライアンス面でのサポートなども行います。
許可申請の代行を申請した場合に行政書士に支払う報酬は相場としは40万円~60万円(事務所によってはこれより低かったり高かったりする場合もあります)といったところでしょうか。
税理士
会計記帳や決算書の作成など会計処理全般を担います
社会保険労務士
運送会社を経営するには、社会保険の適用事業所にならなければなりません。就業規則や三六協定などを労働基準監督署に提出する義務もあります。
就業規則や雇用契約等を作成するのも社会保険労務士になります。
弁護士
契約問題や労働者の未払い賃金、交通事故等、法律、訴訟などの分野で必要になるのが弁護士です。
司法書士
会社登記簿、不動産登記簿など登記に関する部分を担当できるのが司法書士になります。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。