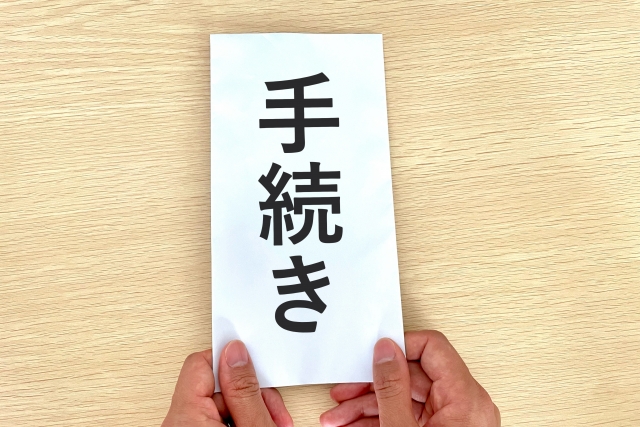
農地を相続した場合にはどのような手続きがあるでしょうか?
通常、農地の権利移転(所有権)、や権利設定(賃貸借)がある場合には、農地法の「許可」が必要です。
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法
しかし、「相続人」が遺産分割や遺贈により農地を取得する場合には、農地法3条の許可は不要となっています。
(「相続人以外」に「特定遺贈」する場合には、許可が必要になります。)
農業委員会に対する届出
農地法3条の許可が不要の場合には、農地法3条の3の規定に基づき、農地取得の届出を行う必要があります。
これは、遺産分割や遺贈のように3条許可が不要な場合においては、農業委員会は農地に関する権利関係の移動を把握することができないためです。
農地法3条の届出は、農業委員会が農地の権利関係を把握することで、農地を適正かつ効率的に利用するための制度であると言えます。
農地法3条の届出の具体的手続き
農地法3条の届出は、取得した農地の存在する農業委員会(市町村)に対して行います。
相続した農地が複数の市町村に点在している場合、それぞれの市町村に届出を行う必要があります。
また、相続により複数の相続人が農地を取得した場合、農業委員会への届出は各自が行う必要があります。
届出は、相続発生を知った日(農地等について権利を取得したことを知った時点)から10カ月以内とされています。
法第3条の3関係
農地等についての権利取得の届出は、農業委員会が許可等によっては把握できない農地等についての権利の移動があった場合にあっても、農業委員会がこれを知り、その機会をとらえて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするものである。この届出の取扱いについては、法令の定めによるほか、次によるものとする。(1) 法第3条の3に基づき届け出なければならないこととされている農地等についての権利取得は、具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による権利取得をいう。
(2) 「遅滞なく」とは、農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内の期間とする。
(3) なお、この届出は、法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではないことに留意するものとする。例えば、届出をしたことにより時効による権利の取得が認められるというものではない
農林水産省:「農地法関係事務に係る処理基準について」より一部抜粋
届出書の様式や必要な添付書類は市町村により異なります。所定の届出書に加え、取得した農地の登記事項証明書や遺産分割協議書、遺言書を添付する場合もあります。


農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。






