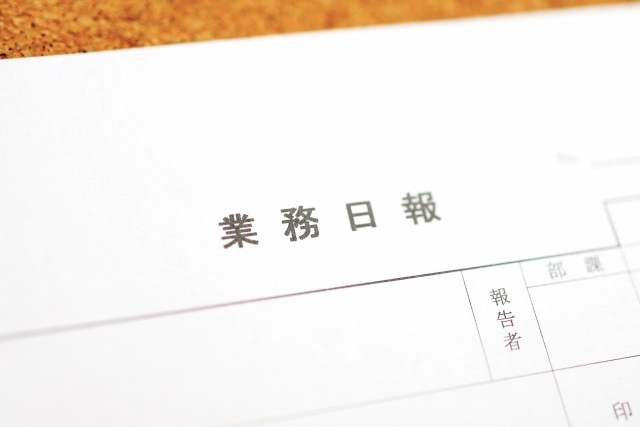点呼とは、運行管理者(補助者)が行い、運転手の乗務前後に行われます。対面で実施する事が基本となります。
乗務前は、運転手本人から健康状態、酒気帯びの有無、日常点検の報告を求め、それに対して安全を確保するために必要な指示を出します。
乗務修了後は、乗務した自動車、道路、運行の状況、酒気帯びの有無、他の運転者と交代した場合には、交替運転者との通告について報告を受けます。
乗務前と乗務後のどちらかが、「やむを得ず」対面で点呼ができない場合は、「電話その他の方法」で点呼を行います。
長距離運行等より乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない場合は、「乗務の途中」で少なくとも1回電話その他の方法により点呼を実施しなければなりません。
「やむを得ない」場合とは、遠隔地で乗務開始または、終了するため、乗務前または乗務後の点呼が営業所において対面で出来ない場合のことをいいます。
「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等運転者と直接対話できる方法のことをいいます。電子メール、FAX等一方的な連絡方法は該当しません。また、電話その他の方法による点呼は運転中に行ってはいけません。
営業所と車庫が離れている場合の点呼
「一般貨物自動車運送事業の許可」(以下、運送業許可)を取得するためには、要件をクリアしなければなりませんが、「営業所」と「車庫」も要件の一つになっています。
点呼場所をどのような所に定めるかは、決まった定義はありませんが、点呼場所には、点呼要領を表した掲示、指導の重点項目、時計、鏡、運転者の立つ位置の表示および必要な帳簿類の備え付けなどある程度の環境作りが必要であるため、通常「営業所」で行われるのが一般的だと思います。
貨物運送業は自動車を使って運送を行うため、自動車の保管場所である「車庫」は当然必要になります。
この「車庫」については、基準があり、原則として営業所に併設している必要がありますが、運送業許可では一定の距離内であれば、「営業所」から離れた場所であっても、認められます。
ここで問題となるのが「点呼」です。点呼は対面で行うことが基本です。
この場合どうするかというと、点呼実施者である運行管理者または、補助者を車庫へ派遣して点呼を行うことになります。
車庫をどこにしようか決める場合には、こういったことも配慮して選ぶ必要があります。
運送業許可のことなら、運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。



.jpg)