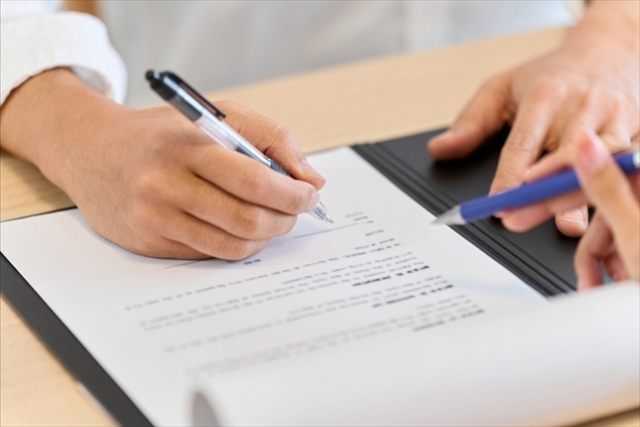農地法3条は農地の権利設定や移転について許可制であることを規定しています。
つまり農地の売買や貸し借りには許可がいるということです。
農地を貸し借り等する場合、一定の許可基準を満たせていれば許可が下りるのですが、以下のような場合には許可が取り消されてしまいます。
農地法3条許可が取り消される場合
- 農地法3条の許可を受けた者が農地を農地として使っていない(農地転用など)
- 農地法3条の許可を受けた者が耕作をしていない
- 上記2つの理由があり、かつ賃貸借等の契約を解除しない
- 上記の事をなおすように勧告されたにもかかわらず、言う事をきかない
農地の売買や貸し借りの場合は、その農地で農業を営むことが前提で許可されています。
そうにもかかわらず、農業をしなかったり、勝手に他のことをしたり(駐車場等)して、さらには契約も解除せず、注意も聞かないといった場合ですね。
相当悪質なケースではありますがその時には許可は取り消されることとなります。
許可が取り消される事で、契約は解除され農地は元の所有者に戻ることになります。
農地法3条の許可が取り消されて、農地がほったらかしになりそうなとき
農地を借りた側が、農業をしなかったり、勝手に転用したりしていると許可が取り消されます。
許可が取り消されて農地が元の所有者に戻ったとしても、元の所有者の事情によっては、農地がほったらかし(遊休化)になってしまう恐れがあります。
例えば、元の所有者が高齢化で農業できないとか、後継者がすぐに農業できないとかなどです。
農地法は農地を守る法律ですので、遊休農地になってしまうと具合が悪いのです。
そのため農地法では、上記のような恐れがある場合には、元の所有者に対して農地の所有権の移転や権利の設定のあっせんを行うことになっています。
例えば農地中間管理機構(農地バンク)に農地を貸したりといったことです。
この農地中間管理機構が元の所有者から借り受けた農地を新たな担い手に貸し付けたりといったことをおこないます。
こういったことを行い、できるだけ農地が遊休化(ほったらかし)することを防いでいます。
農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターにおまかせください。