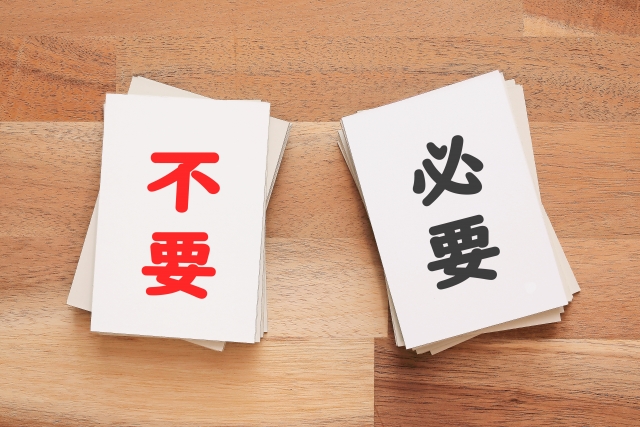農地に家を建てたり、駐車場にしたりなど農地を農地以外にすることを農地転用といいます。
国や国民の限られた資源である農地は農地法という法律により守られており、農地転用には厳しい規制がかかっています。
自分のために農地転用するには農地法4条の許可(届出)、転用目的で他人に譲る場合には農地法5条の許可(届出)が必要となります。
農地転用の許可を得るには、農地転用をしても影響が少ない土地(市街化にある農地など)を選ぶことや、家や駐車場にすることが出来る資力や計画等の要件をクリアしている必要があります。
許可要件を満たしているかどうかについて、様々な書類を収集、提出・提示等で確認されることになります。
農地法5条許可等の申請の際にこの書類に関して、抵当権者の同意書がいるのか?いらないのか?といった問題が生じる事になります。
農地を転用する際に抵当権者の同意は必要か?(市街化区域)
市街化区域とは都市計画法で定められた市街化を促進する区域のことをいいます。市街化区域内の農地(生産緑地を除く)を農地転用する場合には、農業委員会に農地転用の届出をする必要があります。届出の受理通知書が交付されるまでは、その転用事業に着手してはならないとされています。
この届出に当たっては、農地法5条の添付書類として、
- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書
- 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき農地法18条1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面
が必要とされています。(農地法事務処理要領より)
その中で、抵当権者の同意については添付書類として規定がされていませんので、農地法では必ずしも必要ではない書類と考えられます。
農地を転用する際に抵当権者の同意は必要か?(市街化調整区域)
市街化調整区域ではどうでしょうか?
市街化調整区域とは都市計画法で定められた市街化を抑制する区域になります。
市街化調整区域の農地転用に当たっては、農地法4条もしくは5条の許可を得る必要があります(都道府県知事許可)。
農地転用の許可を得るには、前述したように許可要件をクリアする必要があります。
許可要件の基準の一つに転用事業計画の実現性が問われますので、その他参考となるべき書類として、同意書等が求められることもあると言えます。
申請書には、次に掲げる書類を添付させる。
・法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
農地法関連事務処理要領より一部抜粋
・ 申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
・ 申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び附近の状況を表示する図面(縮尺は、10,000分の1ないし50,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面( 縮尺は、500分の1 ないし2,000分の1 程度。当該事業に関連する設計書等の既存の書類の写しを活用させることも可能である。)
・当該事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(例えば、次に掲げる書面又はその写しのように、資力及び信用があることを客観的に判断することができるものとすることが考えられる。)
a 金融機関等が発行した融資を行うことを証する書面その他の融資を受けられることが分かる書面
b 預貯金通帳、金融機関等が発行した預貯金の残高証明書その他の預貯金の残高が分かる書面(許可を 申請する者又はその者の住居若しくは生計を一にする親族のものに限る。)
c 源泉徴収票その他の所得の金額が分かる書面
d 青色申告書、財務諸表その他の財務の状況が分かる書面
・ 所有権以外の権原に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面
・当該事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合において、これを了しているときは、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書( 意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
・当該事業に関連する取水又は排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
・その他参考となるべき書類(許可申請の審査をするに当たって、特に必要がある場合に限ることとし、印鑑証明、住民票等の添付を一律に求めることは適当でない。)
私法上の問題
農地法関連事務処理要領等でもわかる通り、抵当権者の同意書は必ず用意しなければならない書類ではありませんが、同意書を必要とする自治体は多くあります。
抵当権者としては、農地を担保にお金を貸していますので、所有者が変わり、農地も転用するとなれば想定外のことでしょうし、転用目的で農地を譲り受けた人も譲り受けた後で、抵当権を実行されてしまうと困ります。
こういったことことから、自治体では抵当権者の同意書を求めるところが多いのかもしれません。
館山市のHPに参考になるQ&Aがありましたので以下に掲載いたします。
Q:仮登記、抵当権、差押の登記がなされた農地があるが、所有権移転や農地転用の申請できますか ?
A:抵当権の設定実行や仮登記は、私法上の問題であり農地法上の問題ではありませんので、申請は可能です。
館山市HPより
ただし、通常の農地の売買等の場合と同様に、許可、不許可については農地法の許可基準により審査されます。明らかに耕作や転用事業の実現に支障を及ぼすと判断される場合には、同意を書面によって確認してからの許可となる場合もあります。
仮登記は順位保全のための予備的な登記であり、仮登記自体には本登記への対抗力はないので仮登記のある土地を第三者に所有権移転をすることは可能ですが、仮登記の権利者が本登記をした場合には、第三者の所有権は抹消されます。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。