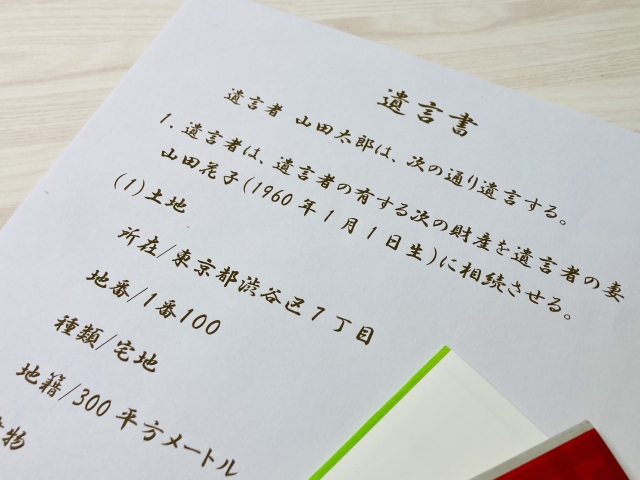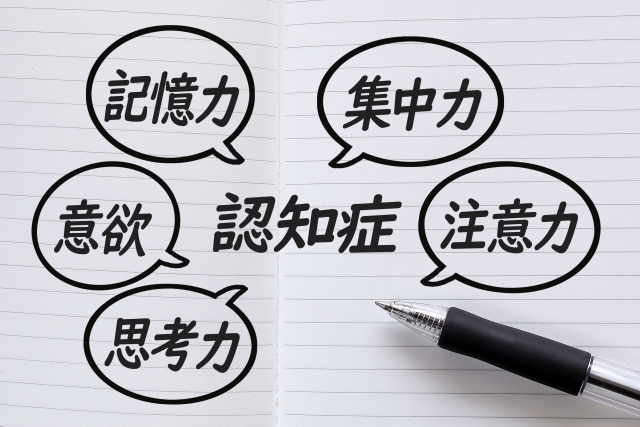令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記の義務化とは、
- 不動産(土地・建物)を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になり、法務局に申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象です。(ただし、3年間の猶予期間あり) - 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
相続登記義務化の背景としては、「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題が発生したいるためです。
この問題の解決のため、令和3年に法律が改正され、「任意」であった相続登記が「義務化」となりました。

不動産を相続した場合、具体的にはどうすればよいのか?
では、不動産を相続した場合は具体的には、どのように対応すればよいのでしょうか?
相続人の間で早めに「遺産分割の話し合い」を行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をしなければなりません。
相続人申告登記
早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にすることにより、義務を果たすこともできます。
「相続人申告登記」とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。
具体的には、
- 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
- 自らがその相続人である旨
を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申出ることで、申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)。
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
添付書類としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。
遺言がある場合
遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記申請(相続人申告登記でも可)を行う。
まとめ
- 遺産分割の話し合いがまとまった → 遺産分割の結果に基づく相続登記(不動産の相続を知った日から3年以内)
- 早期に遺産分割をすることが困難 → 相続人申告登記(不動産の相続を知った日から3年以内)
(遺産分割が成立した場合にはその内容で登記申請をしなければなりません。)
※令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります。
「相続登記の義務化」は令和6年4月1日から始まりますが今のうちから準備をしておくことが重要です。
遺言・相続のことなら、大阪相続・遺言アシストステーションへお気軽にご相談ください。
※今回の記事は、法務局のHP等を参考にして、「相続登記義務化」の一般的な内容についてお伝えしました。上記サイトは行政書士事務所が運営しておりますので、「登記」に関するご相談はお答えすることができません。予めご了承ください。