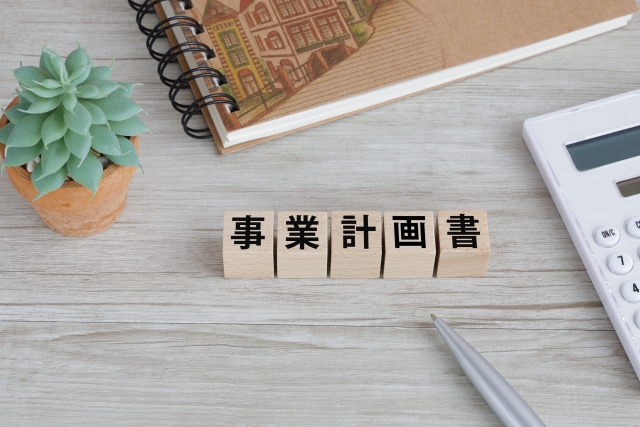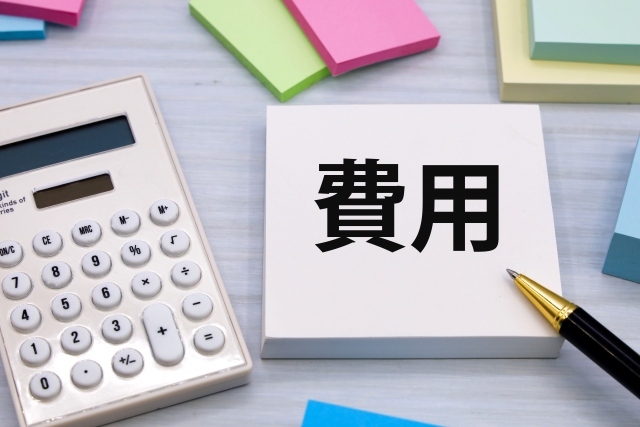農地を相続した場合は、農地法3条の3の規定により、届出をしなければなりません。
提出先は、農地の所在地を管轄する市町村の農業委員会になります。
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
農地法
届出書の記入方法
届出書の様式などは、自治体(農業委員会)ごとに用意してある場合が多いので、自治体のHPなどを確認してみましょう。
また、添付書類としては名義変更後の登記事項証明書などを必要とする自治体がありますが、添付書類も自治体毎に異なるので事前に確認するようにしましょう。

まず、住所・氏名については、農地を相続した人の情報を記入します。
「○○により○○を取得」という部分は、「相続により所有権を取得」とします。
土地の所在等に係る部分は土地登記簿通りに記入していきます。「現況」の内容は土地評価証明書の内容を記入します。
備考欄は特に記入の必要はありません。
権利を取得した日は、被相続人(亡くなった方)の死亡日を記入します。
権利を取得した事由は「相続」、取得した権利の種類および内容は「所有権」とします。
農業委員会によるあっせん等の希望の有無とは、農地を相続で取得したが耕作を続ける事が困難な場合に農業委員会で借受者や買受者などをあっせんを希望するかどうか、ということです。希望があるなら「有」、なければ「無」と記入します。
「無」としておいて、後で「有」にすることも可能です。
相続が発生し、不動産(農地)の相続登記までは終わっていても、この「相続届」の手続きがなされていない場合があるので、忘れないように注意しましょう。
「農地手続」のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。