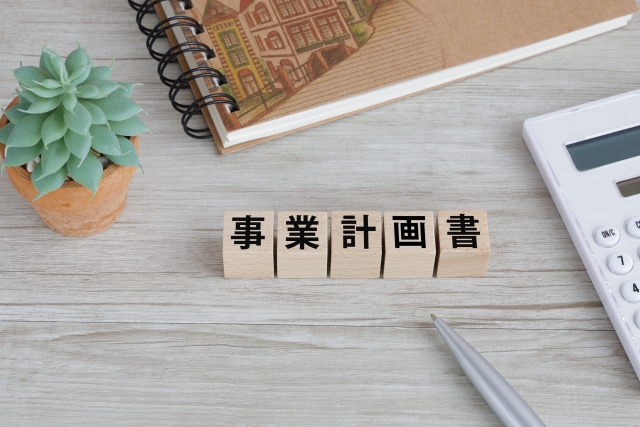農業を営んでいた親が亡くなって、農地を兄弟で相続した場合に困る事はなんでしょうか?
例えば、遺言が無いケースで相続が発生し、親の農地を兄弟で共有分割している状態です。
農業を引き継ぐ者が1人だけなのに、複数人の兄弟で法定相続分に基づき共有分割してしまうと、農地等の権利関係が複雑になります。
ここで、「共有分割」とは、遺産を特定の相続人に単独で取得させず、相続人間の共有としている状態です。
共有分割のデメリット
共有分割には以下の様なデメリットに留意する必要があります。
まず、農地の共有者のうち、農業を営む者は相続税の納税猶予を受けることができますが、農業を行わない者は、取得した農地の共有持ち分について納税猶予を受けることができません。
また、一旦共有分割とした後に共有物分割を行う場合、「農地法の許可」が必要となります。
これに対し、共有持分の放棄であれば農地法の許可は必要ありませんが、共有物分割と異なり、持分が増加する共有者に贈与税、不動産取得税が課税されます。
このように、共有分割を選択すると事後の法律関係が複雑となります。
遺産分割協議、遺言での対策
共有分割をしないために、遺言が無い場合は、「遺産分割協議」をして、農業に従事する者が農業に関する農地等を単独で引き継げるように話し合いをするのがよいのですが、紛争になる可能性も秘めています。
もう一つの方法として、遺言を残していく方法もあります。これは生前に親が遺言を作成しておかなければなりませんが、遺言によって特定の農業承継者に農地所有権を承継させることができます。
この遺言を残しておくことで農地の所有権を特定の相続人に承継させることができ、承継者である相続人が合意をしない限り、相続人らが遺言の内容に反する遺産分割協議をすることはできません。また承継者は単独で所有権移転登記手続きを行うことができるため、他の相続人の協力が難しい場合でも、遺言書によって登記手続きを行うことができます。
農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。