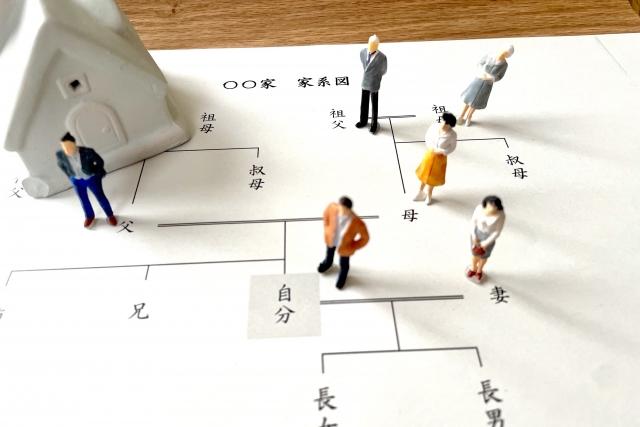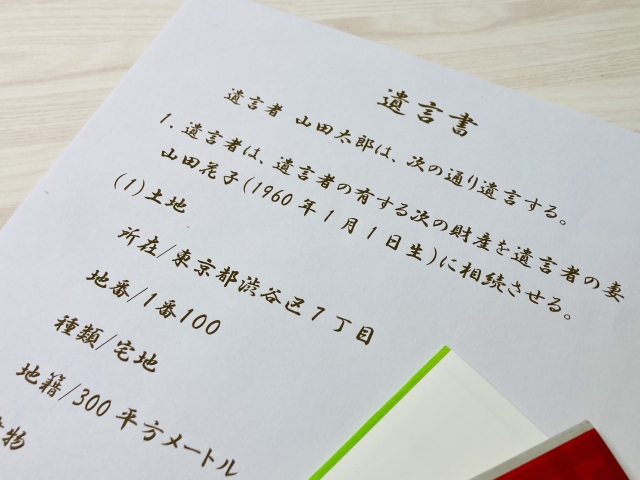
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言があります。
さらに、普通方式遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分けられます。
以下に、普通方式遺言3種類の特徴について説明したいと思います。
※特別方式遺言は、別記事にて説明したいと思います。
自筆証書遺言
全文、日付、氏名を自書、押印し作成する遺言。
- いつでも書くことができる。
- 費用が安い
- 作成方法を誤ると、無効となる可能性がある。
- 自ら保管するので紛失、盗難、改ざんのリスクがある。
- 遺言者の死後、発見されない可能性がある。
- 家庭裁判所の検認(※)が必要となる。
※検認とは遺言が形式的に有効に作成されているかの調査のこと。
2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
これは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度で検認も不要となります。
公正証書遺言
公証役場にて、公証人が遺言者の話を聞き公正証書によってする遺言
- 公証役場にて、保管されるため紛失、盗難、改ざんの恐れがない。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 手数料等、費用がかかる。
- 遺言作成時、証人が2人必要になる。
秘密証書遺言
以下の1~4が必要となります。
- 遺言者が証書に署名し、印を押す。
- 遺言者が封を閉じ、証書と同じ印で封印する。
- 遺言者が公証人と証人2人の前で、自分の遺言書であることと、筆者の氏名、住所を申述(申し述べること)する。
- 公証人が提出日と申述した内容を封書に記載し、公証人、遺言者、証人2人で署名し押印する。
- 開封して、中身を確認しないので秘密が守られる。
- 公証役場にて作成するため、存在の証拠が残る。
- 代筆が可能。
- パソコン等を使用してもよい。
- 家庭裁判所の検認が不要。
- 自ら保管するため、紛失、盗難のリスクがある。
- 開封して万一不備があれば、無効となる可能性がある。
遺言の作成を考えている方は、一番自分にあったやり方で作成しましょう。
相続・遺言のことなら大阪相続・遺言アシストステーションへお気軽にご相談ください。