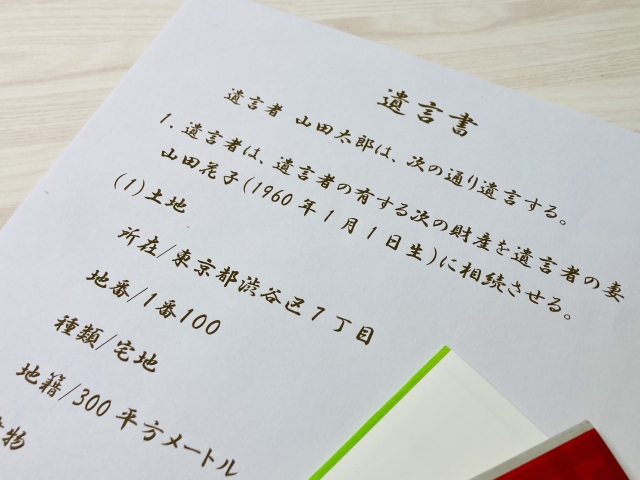遺贈(いぞう)は遺言によって自らの財産を無償で他人に与えること言います。
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
民法
財産を与えられる者を「受遺者(じゅいしゃ)」と言います。受遺者は相続人以外の者でも、相続人でもよいとされています。
遺贈の種類
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類が存在します。
- 特定遺贈
特定の財産を、受遺者に与えることを「特定遺贈」と言います。
一定量の種類物や一定額の金銭であってもよいです。
例えば、
「不動産甲をAに与える」「100万円をBに与える」
などです。 - 包括遺贈
遺産の全部または一定の割合を受遺者に与えることを「包括遺贈」と言います。
例えば
「遺産の半分をAに与える」などです。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することとなります(民法940条)。
例えば
「遺産の半分をAに与える」という遺言がなされた場合、Aが本来の相続人ではなかったとしても、相続人と同一の権利義務を有する事となり、そこで示された割合に応じて債務も負担することになります。
また、遺産については他の相続人と「遺産分割」にも参加する事になります。
しかし、「相続人」と「包括受遺者」が全く同じかというと、そうではありません。
両者には以下のような違いがあります。