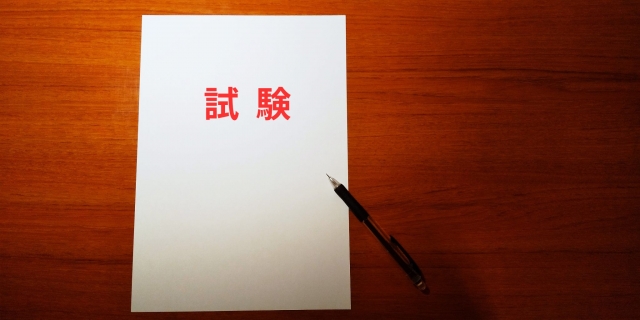
貨物自動運送事業法では以下の用に許可基準について規定しており
(許可の基準)
第六条 国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
三 その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
貨物自動車運送事業法
また、同規則で
(事業の遂行能力の審査)
第三条の六 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
一 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
三 貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
四 一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
五 前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項
貨物自動車運送事業法施行規則
として基準に適合するかどうかに一定の法令知識を求めています。
そのため、許可要件の一つに「法令試験」があります。
では「法令試験」とは具体的にはどういったものなのでしょうか?
近畿運輸局の公示では以下の用に説明されています。
- 試験受ける必要がある申請の種類
- 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請
- 一般貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続認可申請
- 特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
- 受験できる者
- 受験者は1申請で1名のみ。申請者が個人の場合は申請者本人。
法人の場合は許可または認可後に申請する事業に専従する役員(常勤役員のうちの1人という認識でよいです)
- 受験者は1申請で1名のみ。申請者が個人の場合は申請者本人。
- 法令試験について
- 試験は隔月に1回あります。
- 法令試験は申請が受理された翌月に実施されます。
- 試験のチャンスは2回あります。2回とも不合格の場合、却下処分か免許申請の取り下げとなります。(この両者の違いは行政にダメと言われるか、自分でやめるというかの違いで結局は許可できませんという事です。)
- 出題範囲
主に以下のような関係法令から出題されます。
回答は○×で行います。問題数は全部で30問。試験時間は50分。8割正解で合格です。
1問2分弱で回答する必要があります。
資料の持ち込みはできませんが、当日条文集(リンク先:近畿運輸局HP)が配られます。
(近畿運輸局令和6年1月試験結果、過去問回答)- 貨物自動車運送事業法
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
試験対策
輸送の安全を守るには、法令の知識は必須であるため、「法令試験」が許可要件とされていますので、決して簡単な試験ではありません。
当日条文集が配られるので、それを見れば確かに答えは分かるのですが、条文集を見て頂けばわかるのですがかなりの分量なので、どこになにが書いてあるかわかる程度には読み込んでおく必要があります。
また、過去問をある程度解くことで、出題傾向がわかるのでどの分野を重点的に勉強すればいいかもわかりますので過去問演習も効果的でしょう。
運行管理者の出題範囲と重なる部分があるので、運行管理者資格を取るといった方法も有効と思われます。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。






