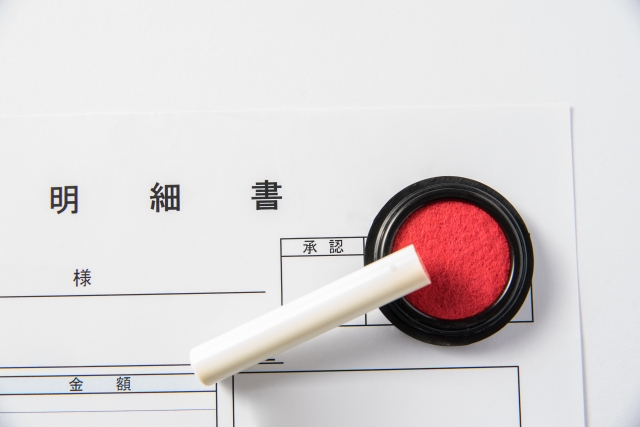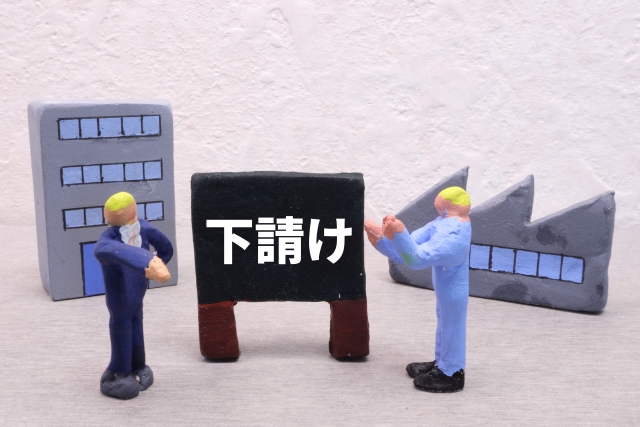
運送業の許可を取得したいと思われている方は「トラック運送業許可」といえば、通常「一般貨物自動車運送事業許可」(以下、運送業許可という)の事を想像されると思います。
運送業許可は、「法人」でも「個人」でも取得することができますが、許可取得の為の要件が厳しく、許可を取得するのはかなり難しいと言えます。
例えば、事業に使う車は5台以上いりますし、車の運転者も雇わなければなりません。車を停めるための車庫や営業所も必要です。さらには、これらを維持していくための資金も必要となります。事業計画の内容によってもかわるので一概には言えませんが必要な資金が2000万円を超えることも珍しくありません。この高額のお金を申請から許可が下りるまでの間キープしておかなければなりません。すでに事業を経営しており比較的資金調達が容易な「法人」に比べると「個人」で運送業許可を取得するとなるとかなりのハードルなのではないでしょうか?
しかし、「個人」でも運送業許可が比較的取得しやすいものがあります。それが「貨物軽自動車運送事業」と「第一種貨物利用運送事業」です。
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業、いわゆる「軽貨物」と呼ばれるものです。前述した「一般貨物自動車運送事業」は「許可」であるのに対してこちらは「届出」となります。届出書を提出して記載内容に問題がなければ、即日でも事業用自動車等連絡書(自家用から事業用ナンバーに換えるために必要な書類)を発行してくれます。ちなみに一般貨物の場合は許可が下りるまで4~5カ月要します。
また要件も比較的易しく、車両は5台以上用意する必要がなく、1台から可能ですし、資金をキープしておかなければならないといったこともありません。一般貨物と比べるとかなりコストを抑えられ事業を開始することができます。
まずは「軽貨物」から始めて、「一般貨物」にステップアップしたり、「軽貨物」事業で培った人脈を生かして。後ほど説明する「利用運送」を始めて事業を展開してもよいのではないでしょうか?
第一種貨物利用運送事業
「水屋」とも言われたりします。自社でトラックを持たず、運送は外注するといったものです。
(利用運送には「ぶら下がり許可」や「第2種利用運送」などもありますが、今回は割愛いたします。)
前述した「軽貨物」よりは、若干ハードルが上がりますが、「一般貨物」よりは「個人」でも比較的取得しやすい部類ではないでしょうか。
第一種貨物利用運送事業は「登録申請」になります。標準処理期間は2~3カ月です。
車両は必要ありませんが、純資産300万円以上が必要です。個人であれば資産調書(主に預金)で確認されます。(法人であれば、直近決算書の貸借対照表純資産の部の合計額(預金や現金ではありません))。
また、外注先との運送委託契約書、保管施設がある場合にはその図面等が必要になります。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にお問い合わせください。