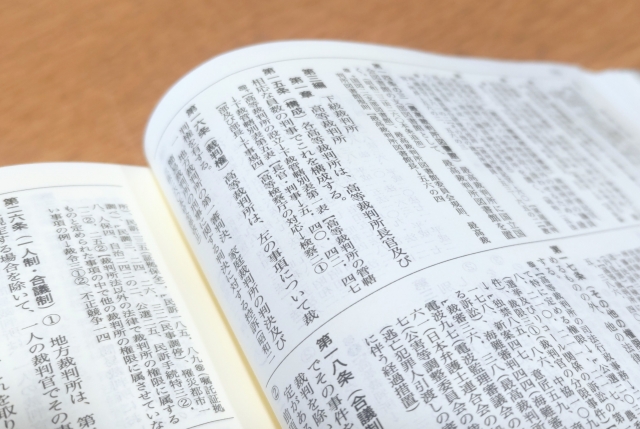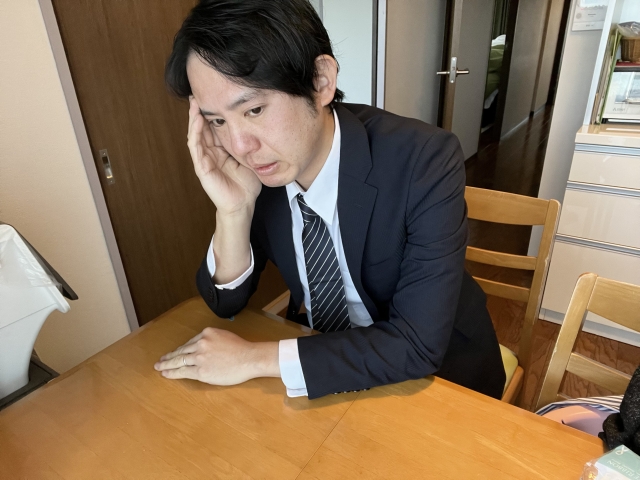
農業をしていた親が他界し、農地を相続した場合などは相続した農地の取扱いに困ることがあります。
親と一緒に農業をしていたなら、農業を継ぐ事で困る事は少ないと思われますが、遠方でサラリーマンとして働いていた場合には、悩むことになるでしょう。
農地を相続したけど、サラリーマンで農業をするつもりがない。ゆくゆくは農業をしたいけどすぐには出来ないなど色々なケースが考えられます。
相続した農地には様々な利用方法があります。
他者に農地として貸し出す
相続人は農地として利用ぜず、「他者」に農地として貸し出します。
農地を貸すために利用できる制度は農地の所在地によって異なります。
「農地法」による貸し出しの場合は、所在地を問わず貸し出し可能ですが使いにくさ(契約の自動更新、解約時の都道府県知事の許可)が指摘されており、特別法を利用する例が増えています。
特別法による貸し出しの場合は「自動更新」や「解約時の都道府県知事の許可」も不要の為、一定期間で農地が必ず戻ってきます。
すぐには無理だけど、ゆくゆくは農業をしたいと考えているのであれば有効な方法です。
特別法には以下のようなものがあります。
- 都市農地貸借円滑化法による貸し出し
相続した農地が市街化区域内の農地で「生産緑地」であればこの制度によって貸し出すことが可能です。 - 農地中間管理事業による貸し出し
市街化調整区域内の農地であれば農地バンクに貸し出すことが可能です。(どんな農地でも貸し出すことが出来るわけではありません。復旧困難な荒廃農地等は借りてもらえません) - 市民農園を開設する
農地としても宅地としても利用せず、農地として譲渡する
自分では、農地としても宅地としても利用せず、「他者」に農地として譲渡します。
農地の所在地によっては、宅地等に転用できず、農地を農地としてのみ譲渡せざるを得ない場合もあります。
相続人が他者に農地として譲渡する場合には、「農地法3条の許可」が必要となります。
宅地等として利用する
自分で農地として利用はしないが、「宅地等」としてアパートや駐車場など不動産事業等のために利用する場合は、宅地等へ転用することになります。この場合には、原則として「農地法4条の許可」が必要となります。
ただし、農地の所在地によっては転用許可がなされない可能性や、逆に「届出」だけで足りる場合もあります。
自分では利用せず、宅地等として譲渡する
自分では農地としても宅地としても利用せず、農地を宅地等として活用するために他者に譲渡する。
上記と同様に農地の所在地によっては宅地に転用することができない場合があります。農地を転用目的で譲渡する場合には、原則として転用目的譲渡として「農地法5条の許可」が必要となります。
農地の所在地によっては5条の許可がなされない可能性や、逆に「届出」だけで足りる場合もあります。
まとめ
現在サラリーマンで、農地を相続した場合には、ケースによって色々な利用方法があることが分かっていただけたと思います。
農業をするつもりがないなら、農地を宅地等に転用する事や、農地のまま他人に売却したり、転用目的で売却したりすればよいですし、いずれ農業をするつもりなら特別法による貸し付け等が有効です。
上記以外にも税金(納税猶予等)に関する事も十分検討して利用方法を決定するようにしましょう。
農地手続の事なら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。