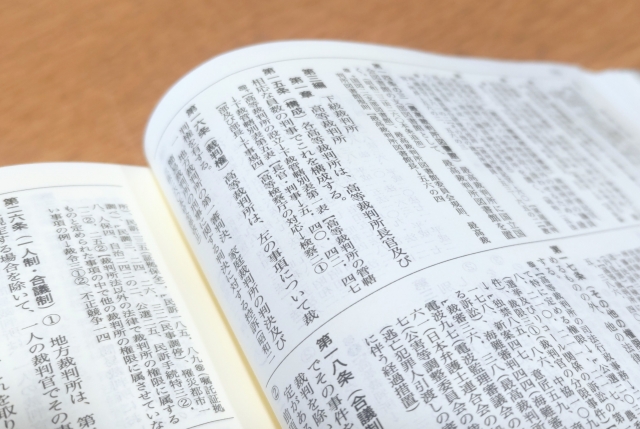農地を貸し出す方法としては、選択肢がいくつかあります。
「農地は貸したら返ってこない」
ワケではなく、実は様々な方法(法律)があります。
農地を貸し出す方法
農地所有者が第3者に農地を貸し出す方法としては、農地法のほかに
- 農業経営強化基盤促進法
- 都市農地貸借円滑化法
- 農地中間管理事業法(農地バンク)
などがあります。
このうち、農業経営基盤強化促進法において、農地を貸し出すこと等を特に「利用権設定」と呼びます
農地の貸し出し方法が複数あるので、
農地の貸し出し方法を決める時は、農地の所在地(市街化区域かどうか)や契約期間の更新の有無、賃料の有無などを確認、検討したうえで行うことができます。
農地法による農地の貸し出し
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下省略)
農地法3条1項
農地法ではこのように定めています。
所有する農地を、他の農家が農地として利用するために賃借権の設定をする場合、農地の所在地がどこであるか(市街化区域、市街化調整区域)にかかわらず、農業委員会の許可が必要です。
農地法(農地法18条)による賃貸借契約の解約
農地法で、他の農家に賃貸借契約により農地を貸し出した場合、期間が満了しても法定更新されます。
農地所有者が賃貸借契約を解約するには、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可が無ければ解約等の効力が生じません。
なお以下のような場合はこの許可が不要となります。
- 合意による解除(農地等の引き渡しの6カ月以内に成立したもので書面になっているもの)
- 農事調停によるもの
- 10年以上の期間の賃貸借についての更新拒絶
- 農地等が適正利用されておらず事前に農業委員会に届け出ている場合
農地法以外による農地の貸し出し
農地法以外での農地の貸し出し等の方法としては、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定と、都市農地貸借円滑化法に基づく農地の貸し出しがあります。
これらの方法であれば、(各法律の詳細は別記事にしたいと思います。)
農地法の許可を受けることなく、農地の貸し出しが可能であり、貸借期間が法定更新されることもありません。
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法は、効率的かつ安定的な農業経営の育成等を目的とした法律です。
都市計画法上の市街化区域を除いた市町村の全域を対象として利用できます。
農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定をする場合は、農地法3条の許可は不要とされており、農地の賃貸借の契約期間が満了したときは法定更新の適用がないとされるなど、安心して農地を貸せる仕組み等が定められています。
都市農地貸借円滑化法
都市農地貸借円滑化法は、市街化区域の農地のうち生産緑地の貸借が安心して行える仕組みを定めています。
借主が作成した事業計画について市町村長の認定を受ければ、農地法の許可をうけることなく農地の貸し出しを行うことができます。
この法律でも、農地貸し出し期間の法定更新はありませんし、解約等のために許可を受ける必要はありません。
これにらにより、都市農地の所有者は農地を貸しやすくなっています。
農地手続に関するこちなら農地手続大阪サポートセンターにおまかせください。