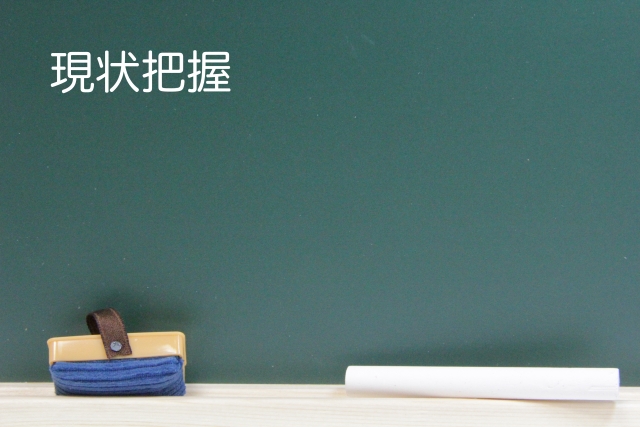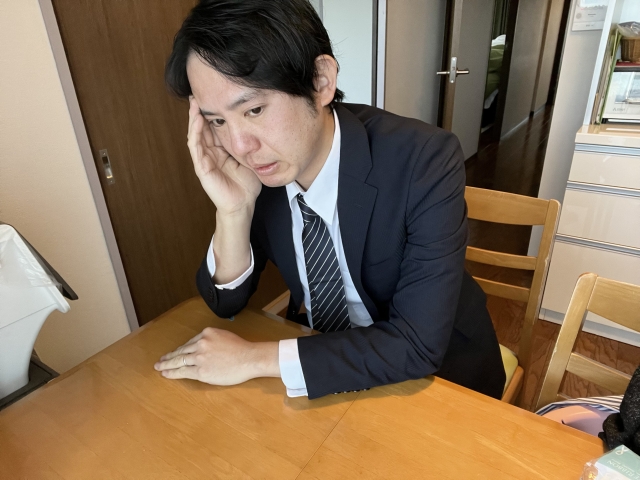農地を相続したけど自分が農業をしない場合は、農地を手放したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?
では、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?
農地を手放す前に注意することがあります。それは被相続人(亡くなった方)が贈与税や相続税の納税猶予を受けていた場合です。
贈与や相続の際に農地の承継者が農業を営む場合にはこういった税制優遇をうけられるのですが、被相続人が農業を営んでいたのであればこれらの納税猶予を受けていた可能性があります。
亡くなった方(被相続人)から相続した農地を手放す場合、方法によっては、これら猶予が確定してしまい。納税猶予税額の全部、又は一部の納付義務が生じる可能性があり、思わぬ負担になることがありますので、事前に十分確認するようにしましょう。
また、農地を承継するタイミングにも注意が必要です。こちらは相続ではないのですが、例えば被相続人が存命の時(相続発生前)に農地を贈与するとなると、相続人が農業をしないということであれば、農地を農地のまま承継することは難しいです。(農業をしない人には農業委員会は許可しません)
となると農地を農地以外(農地転用)のもの(例えば宅地など)にするための権利移転(農地法5条許可)の方法により相続人に農地を承継する形になり、そうすると本人(被相続人)が贈与税または相続税の納税猶予を受けている場合には、相続発生前の譲渡により、納税猶予税額の納付義務が生じる可能性があります。
これに対して、相続発生後の承継の場合には、遺言や遺産分割協議で農地を承継する場合には、農業委員会へは届出だけでよく、本人(被相続人)が贈与税または相続税の納税猶予を受けていた場合でも、それが免除される可能性があります。
つまり、本人(被相続人)の納税猶予を受けていた税額が「相続発生前」と「相続発生後」で、納付義務が生じるのか免除されるのかで変わってくるという事です。
前置きが長くなりましたが、承継した農地を利用する方法(手放す方法)としては
- 農地を貸す
- 農地を譲渡する
- 農地を転用する
- 相続を放棄する
等が考えられます
農地を貸す
農地を農地として貸し出す方法です。貸し出し方法も農地法によるもの、都市農地貸借円滑化法によるもの、農地バンクに貸し出すものなど様々です。
農地を譲渡する
農地を農地として譲渡する場合には農地法3条の許可が必要となります。農地法3条の許可は一定の条件をみたしたものに農地を譲渡できるとしています。例えば農家などに農地を譲渡する場合は農地法3条の許可を得られる可能性は高いと言えますが、農家でない者に農地を譲渡するとなるとハードルが高いと言えます。
農地を転用する
農地を農地以外にする(農地転用)ことも方法の一つです。農地を農地以外にすることとは例えば宅地にしたり、駐車場にしたり、といったことです。
自分の農地を農地転用するには農地法4条の許可、譲渡目的で農地転用するには農地法5条の許可が必要です。農地を転用するには農地法の許可が必要なのですが、農地の所在している場所によって難易度がことなってきます。
農地法は農地を守る法律でもあるため、農地転用は厳しく規制しています。市街地の中にポツンとあるような農地なら農地転用の可能性は高いと思われますが、見渡す限り農地というような場所は農地転用の許可は難しいでしょう。
また、農地の所作在地(市街化調整区域)によっては建物が建てられないといったこともあるので注意が必要です。
相続を放棄する
被相続人の財産や負債を一切了承しないことを希望する場合は、相続放棄することも考えられます。相続放棄をすれば農地を相続することもなくなります。
また、財産が農地しかない場合で、自分が農業をしないけど、他の相続人が農業をする場合には農業を承継する相続人に遺産を集中する場合にも相続放棄の方法は有効です。
農地手続のことなら農地手続大阪サポートセンターにお気軽にご相談ください。