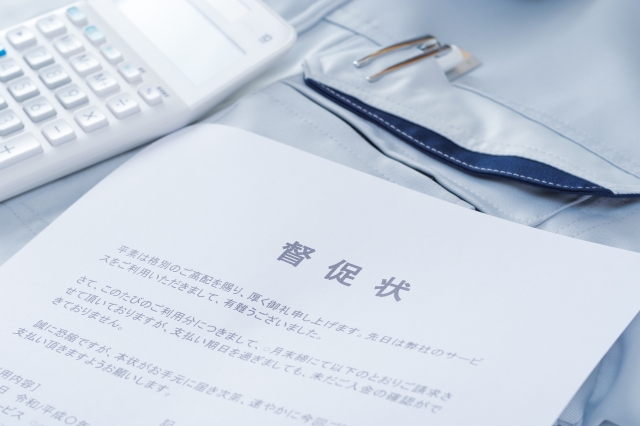
人が亡くなって何らの手続きも取らない(なにもしなかった)場合には、相続人はその人の財産、借金などを全て相続(単純承認)することになります。
手続をした場合、相続人の対応は3つ用意してあります。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三つです。
それぞれ要約すると
- 単純承認
- 無限(プラスの財産、マイナスの財産全て)に亡くなった方の権利義務を承継します。
- 限定承認
- はプラスの財産(預金等)とマイナスの財産(借金等)をそれぞれ相殺して、もしプラス分が残ればそれを相続し、マイナスの財産が残ればそれは相続しないというもの
- 相続放棄
- 読んで字のごとく、一切何も相続しないというもの(初めから相続人ではなかった扱いとなります)
それぞれの詳細は割愛させて頂いて、この3つの対応のどれかを選べる期間が存在します。
その選べる期間の事を熟慮期間といいます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない
民法915条
民法ではこのように規定されていて、熟慮期間は3カ月となっています。
ここでタイトルのお話になるのですが、自分が相続人になったとして自分と近い人が亡くなった場合には、だいたい財産がこれくらいで、借金がこれくらいでとわかると思うのですが、疎遠になっている人の相続人になった場合はそういった状況がわからないものです。
そこで問題となるのがこの熟慮期間です。(自分が疎遠になっている人の相続人になった場合)
財産も借金もなにもないと思っていて、熟慮期間が経過してしまった場合単純承認となりますが(プラスもマイナスも全て相続する)、あとで借金があることが判明した場合、どうしようもないのでしょうか?
判例では以下のようになっています
相続人が右事実(相続の開始と自らが相続人となったこと)を知った場合であっても、右各事実を知った時から3カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人(亡くなった人)に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当ではないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき・・・
最判昭和59年4月27日
判例では信じるについて相当な理由があると認められた時には、熟慮期間の起算点(3カ月の出発点を相続が発生した時を知ったときではなく、財産の状況が分かった時からカウントするという意味)をずらすべきだとしている。
ですので、この判例のケースで言えば借金が分かってからどうするのか?3カ月間考えることができることになります。
ただし、この判決で示されてた要件はかなり厳格であり
単純に「知らない借金があったから、起算点をずらせる」わけではないので注意が必要です。



